「幼年期の終り」とクラーク作品雑感 [映画・文学・音楽]
昨夜発表された日本アカデミー賞の結果です。
作品賞は「新聞記者。主演男優賞の松坂桃李、主演女優賞のシム・ウンギョンとあわせて主要3部門。この映画についてはすでに書いたように悪くはないが核心への迫り方がちょっと緩いというのが私の感想です。
https://animalvoice.blog.ss-blog.jp/2019-12-16
まあ、ほかに(邦画全作見ているわけではありませんが)これといった作品もないので妥当なところでしょうか。驚いたのは「翔んで埼玉」。出だしは快調なんですがだんだんつまらなくなり最後はクソ映画で終わりました。このゴミのような映画が監督賞と脚本賞とは、びっくりポンのポン。映画に対する私の評価基準が飛んで、いや翔んでっちゃいました。
( >_< )( >_< )( >_< )
【追記】ツイッターを見ると、「新聞記者」ではなく「捏造記者」だとか、「赤デミー賞」だとかネトウヨたちが悔し紛れにツイートしていますが、彼らはこの映画を見ているんでしょうか。見てもいないものを噂のみで評価できるとは、サスガです。映画は映画で評価すべきであり、政治で評価するものではないのですが、もちろんネトウヨはこのブログの雑文など読んでいないでしょう。
https://animalvoice.blog.ss-blog.jp/2019-11-11
………………………………………………………………………………………………………………………………
NHKのEテレに「100分de名著」という番組がある。
もともとは「一週間de資本論」として始まったもので、TBSの「Nスタ」などで見かけることがある堀尾さんがMCだったような記憶がある(最近、ボケが進んでいるので断言はしない(^^;)。「100分de名著」というタイトルになってからは25分×4回の放送でMCは伊集院光。ドストエフスキー「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」、陳寿「三国志」、「ファーブル昆虫記」、「小松左京スペシャル」などいくつか見たが全話見たものはない。
その「100分de名著」がこの3月は「アーサー・C・クラークスペシャル」ということで、「太陽系最後の日」「幼年期の終わり」「都市と星」「楽園の泉」をとりあげている。映画としても有名な「2001年宇宙の旅」が章立てされていないのは、別に取り上げたことがあったのか、「幼年期」との関連でとりあげられるのか、クラーク作品全体のテーマとも重なるのでしめくくりとしてとりあげるのか、そのあたりはこの雑文を書いている2020.03.05にはまだまだわからない。
クラークの作品については以前思いつくままだらだらとを書いたことがあるが、今回、「幼年期の終り」を読み直してみたので補筆しながら再度取り上げ思いつくままとりとめもなく書いててみることにした。SFやクラークに関心のない人は、スルーしてもらいたい。m(__)m
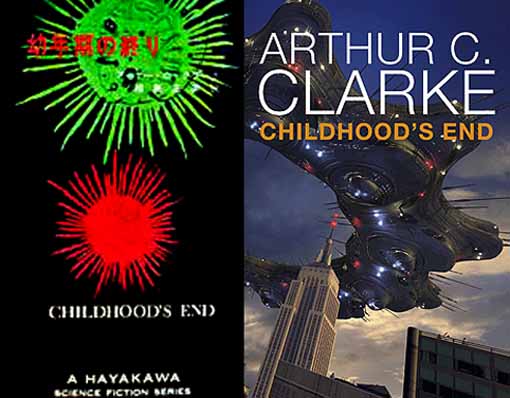
「幼年期の終り」をメインに、SF作家アーサー・C・クラークの作品について思いつくまま書いてみたい。評論でも批評でもない単なる印象感想なので、クラークについて深く知りたいと思う人はパスしたほうが時間の無駄遣いにならないと思う。
どうでもいいことだが、私が所有している「Childhood's end」のタイトルは「幼年期の終り」。ハヤカワ書房・福島正実訳で、創元SF文庫の沼沢洽治訳では「地球幼年期の終わり」、最近出た光文社の古典新訳文庫・池田真紀子訳では「幼年期の終わり」となっている。この作品はアメリカではテレビのミニドラマ・シリーズにもなっているが特撮もダメダメの出来の悪いドラマなので、ここでは触れないこととする。
https://meisoud.blog.ss-blog.jp/2016-09-17
クラークの名作(と言われている)「幼年期の終り」は、もう3、4回は読んでいることになるはずで、確かに想像力を刺激する作品であることは間違いなく、私も傑作だとは思うのだが、クラークの欠点もまた見えてしまう作品である。手放しに絶賛していいのか、という気持ちはある。とまれ、私にとってこの作品はいろいろな意味で思い出があるので、まずその話から。
今から半世紀近くも昔のことなのだが、SFという言葉はまだほとんど認知されていなかった。ハヤカワSFシリーズ(当初はHF=ハヤカワファンタジーと称していた)が細々と出ているだけで、創元推理文庫のSFセクション(創元SF文庫なるものはまだなかった)の第1弾フレドリック・ブラウンの「未来世界から来た男」がようやく出たころのことである。
「彼らのための三章」という私の駄作を読んだ奇特な人には繰り返しになるが、SFマガジンという雑誌の存在に気がついたのは、ちょうどそんなころのことだった。シャレた表紙が印象的で、へえ、こんな雑誌があったんだ、と買ってしまったのだ。
SFマガジンの43号である。
SF=Science Fictinなんて言葉は知らなかったが、いわゆる空想科学小説なるものはウエルズやハインラインなどの子ども向けに訳されたものを読んでいて好きだったし、「大人向けの空想科学小説」という物珍しさもあって隅から隅まで読んだ。その雑誌の中に「人気カウンター」というものがあった。つまり、その号の雑誌に載っている全小説に順位をつけて応募すると抽選で5人だったかにハヤカワSFシリーズの最新刊が当たるというものである。詳細は覚えていないが、アシモフの「夜来たる」という中編を1位にしたことだけは覚えている。すると、その最初の投票はがきが見事当選したのだ。
で、送られて来たのがクラークの「幼年期の終り」だったというわけ。
初めて読む大人向けの長編SFで、これがぞくぞくするほどおもしろかった。
私にとっては、このクラークの「幼年期の終り」とシマックの「都市」、ブラッドベリの「火星年代記」という3冊が当時のSF3大名作となった。
その後、とくにクラークのフアンというわけでもないのだが、気がつけば長編では「火星の砂」「銀河帝国の崩壊」「都市と星」「地球光」「渇きの海」「楽園の泉」「遥かなる地球の歌(ただし私が読んだのはSFマガジンに載った中編)」「2001年宇宙の旅」「2010年宇宙の旅」「2061年宇宙の旅」「3001年終局への旅」「宇宙のランデヴー」など読んでいる。
長編以外では、クラークの実質的処女作でありSFマガジンの創刊号をかざった短編「太陽系最後の日」や「2001年宇宙の旅」の元になったと言われている「前哨」なども読んだ。SFマガジンに不定期に載った「白鹿亭綺譚」なんて連作短編も読んだがこれはあまりおもしろくはなかった。この手のもの、要するにストーリーテラーとしてはアシモフのほうが断然うまい。
あと、あまり話題にはならないが記憶に残っている短編に「時を掃く」という作品がある。宇宙船のコンピュータが故障し軌道計算ができなくなる。ところが偶然、算盤ができる男がおり、乗組員たちはその男に算盤を習って軌道計算をしていくという話である。コンピュータと算盤の取り合わせというのが何とも奇妙におもしろかった隠れた傑作だと思う。
科学エッセーでSFマガジンに連載され後にまとめられた「未来のプロフィル」、映画「2001年宇宙の旅」とのかかわりを書いた「失われた宇宙の旅2001(前出の『前哨』も参考資料として再録されている)」なんてのも読んだ。「未来のプロフィル」には現在の衛星放送の原型とも思える記述があり、半世紀も前の人間の想像力を検証する意味でもおもしろい読み物だと思う。フアンではないとは言うものの、これはけっこうな数ではある。よくこんなに読んだものだと自分でも感心する。
暇なのか、馬鹿なのか(^^;。
ついでに書いておくと、1970年に名古屋で開かれた「国際SFシンポジウム・空想的交通論」でクラークのご尊顔を直接見てもいる。この会議にはクラークをはじめ、フレデリック・ポール、ブライアン・オールディス、ジュディス・メリルといった海外の著名SF作家のほか日本からも星新一、小松左京、石原藤夫、真鍋博にそうそうたる面々が出席していてそれだけでも出席した価値があった。全体において日本、とくに星新一の発言は「いっぱい人工衛星を打ち上げておいてそこから垂れ下がったロープを利用してターザンのように移動する」とか「人間が輪っかになって転がって行く」アホというか奇想天外なものが多く、クラークが真面目にひとつひとつその実現性の可能性について論じていたのが印象的だった。SF用語が頻発するせいもあって、同時通訳のおっさんが何度も「わからん!」とかんしゃくを起こして、その都度、会場の笑いをとっていたなぁ。
(さらについでのついで。まだ50代半ばのクラークはすでにつるっ禿だった。アシモフがかつてこんなことを書いていた。「自分より小説のうまい相手と話すときは科学の話題に話をそらし、自分より科学に精通している相手と話すときは小説の話題に話をそらす。ところがクラークはその両方ともに秀でているので始末に悪い。そんなときは彼の頭を見て優越感に浸るのである」)
いかん、いつものことながら大幅に話がそれた。
今回、久しぶりに「幼年期の終り」を再読してみて思ったのは、クラークという作家は実に発端がうまい、ということだ。私は読んでいない光文社古典新訳文庫の「改訂版」ではプロローグが書き換えられているということだが、私のもっているハヤカワSFシリーズ(当選でもらったやつ)では、こうだ。
米ソの宇宙開発競争に全力をつくしている科学者たちがいる。相手より1日でも早く打ち上げないとと鎬を削る彼らは、ふと空を見上げたとき、自分たちの努力が無に帰したことを知る。空には、彼らの努力をあざ笑うように巨大な宇宙船が無数に浮かんでいたのだ・・・。
「人類はもはや孤独ではないのだ」
実にうまい書き出しではないか。
本書の延長線上にある「2001年宇宙の旅」のプロローグも同じようにうまいので、こちらもちょっとだけ引用してみる。
「今この世にいる人間ひとりひとりの背後には、三十人の幽霊が立っている。それが生者に対する死者の割合である。時のあけぼの以来、およそ一千億の人間が、地球上に足跡を印した。この数字は興味深い。というのは、奇妙な偶然だが、われわれの属する宇宙、この銀河系に含まれる星の数が、またおよそ一千億だからだ」(伊藤典夫訳)
そして、この「まえがき」は次のような印象深い言葉で結ばれている。
「(それほどにも多くの星があり生命が存在する惑星の可能性が考えられるのに)なぜ、そんな出会いがまだおこっていないのだろう?・・・本当に、なぜだろうか?・・・」
うまいなあ。
私だったら、この書き出しを読んだだけで絶対に読みたくなるし、本を買いたくなる(事実、読んでいるわけだが)。と、同時に、「太陽系最後の日」から晩年の「宇宙のランデブー」まで、途中に「幼年期の終り」と「2001年宇宙の旅」という高い山をはさんで、クラークの作品は、人類の未来と地球外知性との接触というテーマで一貫しているのがわかる。事実、そうしたテーマとは一見関係ないように思える「海底牧場」(海底にエリアを作りクジラを食用に家畜化する)でも、クジラの血まみれの解体作業の延長線上に、こうした「殺戮」を地球外生命が見たら何と思うだろう、という視点が語られている。このことについては、後でもう一度触れる。
で、再び「幼年期の終り」に戻るが、この初期と中期とをつなぐ作品にはいい意味でも悪い意味でもクラークの特徴が出ていると思う。
プロローグは上にも書いたように満点に近い。次いで、
第1部 地球とオーバーロードたち
第2部 黄金時代
第3部 最後の世代
という3部に分かれるのだが、魅力的な地の文に対し、登場人物の描写があまりに通り一遍なのが残念である。かろうじて印象的なのは第1部に出てくる国連事務総長のストルムグレンくらいのものだが、彼の誘拐事件など単に話を引き延ばしているだけのような感じさえする。第2部は最も退屈な部分で、パーティーの場面など人物の描き分けがうまくできていない。会話も全く弾んでいない(比べてはいけないのだがトルストイの「戦争と平和」のパーティー場面など素晴らしいの一語に尽きる)。
思うに、クラークの頭の中には地球外生物との接触を経て、人類が何ものかになるラストまでという図式があったのだろう(まさに「2001年宇宙の旅」も同じ図式である)。で、なんとかその間をつなごうとした。つなぎの場面なのでどうしても退屈になってしまうわけだ。
密航する人物にしても残念ながら個性は感じられず、人類の最後に立ち会わせるために作り出したという感が否めない(密航方法が「聖書」でクジラに飲まれたヨナをヒントにしているのは明らかだが、なぜ最後の人間になるのかは、ネタバレしてしまうので書かない)。つまり、ある設定を実現するために、半ば無理矢理作り上げられた人物たちばかりなので、昔の文芸評論家なら手垢にまみれたこんな言葉をはくと思われる。
「人物が全く生きていない」
テーマ、設定ともに抜群におもしろいのに、この部分に関してだけは本当なので困ってしまう。あの「2001年宇宙の旅」にしても、原作、映画ともに人物の印象はほとんど記憶に残らないほど希薄である。考えてみれば実質的な処女作である「太陽系最後の日」も波乱含みの始まりで期待がふくらむものの、途中、地底電車に閉じ込められてもたもたしてとてもうまくまとまっているとは言いがたい。当初から「つなぎ場面」の処理は下手だったわけだ。それでもこの作品が読み継がれているのは、読者が人類の一員であることで素晴らしく溜飲が下がるラストがそれまでの欠点をすべて覆い隠してしまうからだ。
要するにクラークの作品は処女作から最高傑作と言われる「幼年期の終り」、話題になった「2001年宇宙の旅」、晩年の「宇宙のランデブー」に至るまでテーマ、書き方とも(いい意味でも悪い意味でも)終始一貫しているのだ。そんなことから、(めぼしいものはほとんど読んでしまっている今となっては遅いのだが)私はクラーク作品の出来不出来を見分ける重要なキーワードを導き出すことができた。
「会話の少ない小説を読め」
素晴らしく息をのむような状況描写と個性のない人間たちの織りなすドラマなのだから、こういう結論になる。クラークを弁護すれば、世間一般の人間関係などこかへ吹き飛ばしてしまうほど描かれる状況が魅力的かつ鮮烈なのだ。クラークには、人類を継ぐものは人類ではない、それは「2001年」のような機械(コンピュータ)かもしれないし、「幼年期」のような超人類かもしれないという、確固たる信念がある。そうした状況の中では、「人物が生きていない」のではなく「人物が霞んでしまう」のだ。状況描写に場面と比べて人間関係の場面が希薄かつ退屈なのはそのせいなのではないかと思う。だから、クラークの小説は、会話部分が少なければ少ないほどいい。もしも、会話が全然ないクラークの作品があったとしたら、それは間違いなく傑作だと断言してもよい。絶対に読むべし。
※おまけ A.C.クラークの「2001年宇宙の旅」に始まる「オデッセイ・シリーズ」についてはこんな雑文を書いたことがある。関心のある人は、暇潰しにどうぞ。
https://meisoud.blog.ss-blog.jp/2013-05-23

作品賞は「新聞記者。主演男優賞の松坂桃李、主演女優賞のシム・ウンギョンとあわせて主要3部門。この映画についてはすでに書いたように悪くはないが核心への迫り方がちょっと緩いというのが私の感想です。
https://animalvoice.blog.ss-blog.jp/2019-12-16
まあ、ほかに(邦画全作見ているわけではありませんが)これといった作品もないので妥当なところでしょうか。驚いたのは「翔んで埼玉」。出だしは快調なんですがだんだんつまらなくなり最後はクソ映画で終わりました。このゴミのような映画が監督賞と脚本賞とは、びっくりポンのポン。映画に対する私の評価基準が飛んで、いや翔んでっちゃいました。
( >_< )( >_< )( >_< )
【追記】ツイッターを見ると、「新聞記者」ではなく「捏造記者」だとか、「赤デミー賞」だとかネトウヨたちが悔し紛れにツイートしていますが、彼らはこの映画を見ているんでしょうか。見てもいないものを噂のみで評価できるとは、サスガです。映画は映画で評価すべきであり、政治で評価するものではないのですが、もちろんネトウヨはこのブログの雑文など読んでいないでしょう。
https://animalvoice.blog.ss-blog.jp/2019-11-11
………………………………………………………………………………………………………………………………
NHKのEテレに「100分de名著」という番組がある。
もともとは「一週間de資本論」として始まったもので、TBSの「Nスタ」などで見かけることがある堀尾さんがMCだったような記憶がある(最近、ボケが進んでいるので断言はしない(^^;)。「100分de名著」というタイトルになってからは25分×4回の放送でMCは伊集院光。ドストエフスキー「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」、陳寿「三国志」、「ファーブル昆虫記」、「小松左京スペシャル」などいくつか見たが全話見たものはない。
その「100分de名著」がこの3月は「アーサー・C・クラークスペシャル」ということで、「太陽系最後の日」「幼年期の終わり」「都市と星」「楽園の泉」をとりあげている。映画としても有名な「2001年宇宙の旅」が章立てされていないのは、別に取り上げたことがあったのか、「幼年期」との関連でとりあげられるのか、クラーク作品全体のテーマとも重なるのでしめくくりとしてとりあげるのか、そのあたりはこの雑文を書いている2020.03.05にはまだまだわからない。
クラークの作品については以前思いつくままだらだらとを書いたことがあるが、今回、「幼年期の終り」を読み直してみたので補筆しながら再度取り上げ思いつくままとりとめもなく書いててみることにした。SFやクラークに関心のない人は、スルーしてもらいたい。m(__)m
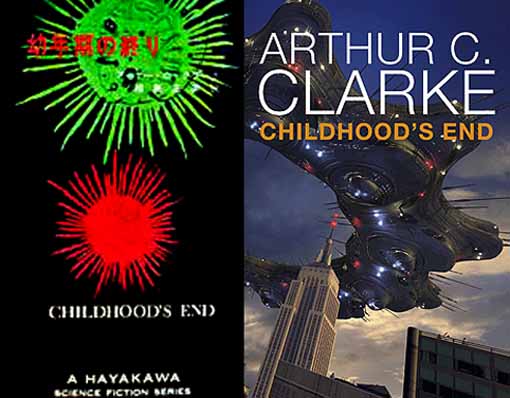
「幼年期の終り」をメインに、SF作家アーサー・C・クラークの作品について思いつくまま書いてみたい。評論でも批評でもない単なる印象感想なので、クラークについて深く知りたいと思う人はパスしたほうが時間の無駄遣いにならないと思う。
どうでもいいことだが、私が所有している「Childhood's end」のタイトルは「幼年期の終り」。ハヤカワ書房・福島正実訳で、創元SF文庫の沼沢洽治訳では「地球幼年期の終わり」、最近出た光文社の古典新訳文庫・池田真紀子訳では「幼年期の終わり」となっている。この作品はアメリカではテレビのミニドラマ・シリーズにもなっているが特撮もダメダメの出来の悪いドラマなので、ここでは触れないこととする。
https://meisoud.blog.ss-blog.jp/2016-09-17
クラークの名作(と言われている)「幼年期の終り」は、もう3、4回は読んでいることになるはずで、確かに想像力を刺激する作品であることは間違いなく、私も傑作だとは思うのだが、クラークの欠点もまた見えてしまう作品である。手放しに絶賛していいのか、という気持ちはある。とまれ、私にとってこの作品はいろいろな意味で思い出があるので、まずその話から。
今から半世紀近くも昔のことなのだが、SFという言葉はまだほとんど認知されていなかった。ハヤカワSFシリーズ(当初はHF=ハヤカワファンタジーと称していた)が細々と出ているだけで、創元推理文庫のSFセクション(創元SF文庫なるものはまだなかった)の第1弾フレドリック・ブラウンの「未来世界から来た男」がようやく出たころのことである。
「彼らのための三章」という私の駄作を読んだ奇特な人には繰り返しになるが、SFマガジンという雑誌の存在に気がついたのは、ちょうどそんなころのことだった。シャレた表紙が印象的で、へえ、こんな雑誌があったんだ、と買ってしまったのだ。
SFマガジンの43号である。
SF=Science Fictinなんて言葉は知らなかったが、いわゆる空想科学小説なるものはウエルズやハインラインなどの子ども向けに訳されたものを読んでいて好きだったし、「大人向けの空想科学小説」という物珍しさもあって隅から隅まで読んだ。その雑誌の中に「人気カウンター」というものがあった。つまり、その号の雑誌に載っている全小説に順位をつけて応募すると抽選で5人だったかにハヤカワSFシリーズの最新刊が当たるというものである。詳細は覚えていないが、アシモフの「夜来たる」という中編を1位にしたことだけは覚えている。すると、その最初の投票はがきが見事当選したのだ。
で、送られて来たのがクラークの「幼年期の終り」だったというわけ。
初めて読む大人向けの長編SFで、これがぞくぞくするほどおもしろかった。
私にとっては、このクラークの「幼年期の終り」とシマックの「都市」、ブラッドベリの「火星年代記」という3冊が当時のSF3大名作となった。
その後、とくにクラークのフアンというわけでもないのだが、気がつけば長編では「火星の砂」「銀河帝国の崩壊」「都市と星」「地球光」「渇きの海」「楽園の泉」「遥かなる地球の歌(ただし私が読んだのはSFマガジンに載った中編)」「2001年宇宙の旅」「2010年宇宙の旅」「2061年宇宙の旅」「3001年終局への旅」「宇宙のランデヴー」など読んでいる。
長編以外では、クラークの実質的処女作でありSFマガジンの創刊号をかざった短編「太陽系最後の日」や「2001年宇宙の旅」の元になったと言われている「前哨」なども読んだ。SFマガジンに不定期に載った「白鹿亭綺譚」なんて連作短編も読んだがこれはあまりおもしろくはなかった。この手のもの、要するにストーリーテラーとしてはアシモフのほうが断然うまい。
あと、あまり話題にはならないが記憶に残っている短編に「時を掃く」という作品がある。宇宙船のコンピュータが故障し軌道計算ができなくなる。ところが偶然、算盤ができる男がおり、乗組員たちはその男に算盤を習って軌道計算をしていくという話である。コンピュータと算盤の取り合わせというのが何とも奇妙におもしろかった隠れた傑作だと思う。
科学エッセーでSFマガジンに連載され後にまとめられた「未来のプロフィル」、映画「2001年宇宙の旅」とのかかわりを書いた「失われた宇宙の旅2001(前出の『前哨』も参考資料として再録されている)」なんてのも読んだ。「未来のプロフィル」には現在の衛星放送の原型とも思える記述があり、半世紀も前の人間の想像力を検証する意味でもおもしろい読み物だと思う。フアンではないとは言うものの、これはけっこうな数ではある。よくこんなに読んだものだと自分でも感心する。
暇なのか、馬鹿なのか(^^;。
ついでに書いておくと、1970年に名古屋で開かれた「国際SFシンポジウム・空想的交通論」でクラークのご尊顔を直接見てもいる。この会議にはクラークをはじめ、フレデリック・ポール、ブライアン・オールディス、ジュディス・メリルといった海外の著名SF作家のほか日本からも星新一、小松左京、石原藤夫、真鍋博にそうそうたる面々が出席していてそれだけでも出席した価値があった。全体において日本、とくに星新一の発言は「いっぱい人工衛星を打ち上げておいてそこから垂れ下がったロープを利用してターザンのように移動する」とか「人間が輪っかになって転がって行く」アホというか奇想天外なものが多く、クラークが真面目にひとつひとつその実現性の可能性について論じていたのが印象的だった。SF用語が頻発するせいもあって、同時通訳のおっさんが何度も「わからん!」とかんしゃくを起こして、その都度、会場の笑いをとっていたなぁ。
(さらについでのついで。まだ50代半ばのクラークはすでにつるっ禿だった。アシモフがかつてこんなことを書いていた。「自分より小説のうまい相手と話すときは科学の話題に話をそらし、自分より科学に精通している相手と話すときは小説の話題に話をそらす。ところがクラークはその両方ともに秀でているので始末に悪い。そんなときは彼の頭を見て優越感に浸るのである」)
いかん、いつものことながら大幅に話がそれた。
今回、久しぶりに「幼年期の終り」を再読してみて思ったのは、クラークという作家は実に発端がうまい、ということだ。私は読んでいない光文社古典新訳文庫の「改訂版」ではプロローグが書き換えられているということだが、私のもっているハヤカワSFシリーズ(当選でもらったやつ)では、こうだ。
米ソの宇宙開発競争に全力をつくしている科学者たちがいる。相手より1日でも早く打ち上げないとと鎬を削る彼らは、ふと空を見上げたとき、自分たちの努力が無に帰したことを知る。空には、彼らの努力をあざ笑うように巨大な宇宙船が無数に浮かんでいたのだ・・・。
「人類はもはや孤独ではないのだ」
実にうまい書き出しではないか。
本書の延長線上にある「2001年宇宙の旅」のプロローグも同じようにうまいので、こちらもちょっとだけ引用してみる。
「今この世にいる人間ひとりひとりの背後には、三十人の幽霊が立っている。それが生者に対する死者の割合である。時のあけぼの以来、およそ一千億の人間が、地球上に足跡を印した。この数字は興味深い。というのは、奇妙な偶然だが、われわれの属する宇宙、この銀河系に含まれる星の数が、またおよそ一千億だからだ」(伊藤典夫訳)
そして、この「まえがき」は次のような印象深い言葉で結ばれている。
「(それほどにも多くの星があり生命が存在する惑星の可能性が考えられるのに)なぜ、そんな出会いがまだおこっていないのだろう?・・・本当に、なぜだろうか?・・・」
うまいなあ。
私だったら、この書き出しを読んだだけで絶対に読みたくなるし、本を買いたくなる(事実、読んでいるわけだが)。と、同時に、「太陽系最後の日」から晩年の「宇宙のランデブー」まで、途中に「幼年期の終り」と「2001年宇宙の旅」という高い山をはさんで、クラークの作品は、人類の未来と地球外知性との接触というテーマで一貫しているのがわかる。事実、そうしたテーマとは一見関係ないように思える「海底牧場」(海底にエリアを作りクジラを食用に家畜化する)でも、クジラの血まみれの解体作業の延長線上に、こうした「殺戮」を地球外生命が見たら何と思うだろう、という視点が語られている。このことについては、後でもう一度触れる。
で、再び「幼年期の終り」に戻るが、この初期と中期とをつなぐ作品にはいい意味でも悪い意味でもクラークの特徴が出ていると思う。
プロローグは上にも書いたように満点に近い。次いで、
第1部 地球とオーバーロードたち
第2部 黄金時代
第3部 最後の世代
という3部に分かれるのだが、魅力的な地の文に対し、登場人物の描写があまりに通り一遍なのが残念である。かろうじて印象的なのは第1部に出てくる国連事務総長のストルムグレンくらいのものだが、彼の誘拐事件など単に話を引き延ばしているだけのような感じさえする。第2部は最も退屈な部分で、パーティーの場面など人物の描き分けがうまくできていない。会話も全く弾んでいない(比べてはいけないのだがトルストイの「戦争と平和」のパーティー場面など素晴らしいの一語に尽きる)。
思うに、クラークの頭の中には地球外生物との接触を経て、人類が何ものかになるラストまでという図式があったのだろう(まさに「2001年宇宙の旅」も同じ図式である)。で、なんとかその間をつなごうとした。つなぎの場面なのでどうしても退屈になってしまうわけだ。
密航する人物にしても残念ながら個性は感じられず、人類の最後に立ち会わせるために作り出したという感が否めない(密航方法が「聖書」でクジラに飲まれたヨナをヒントにしているのは明らかだが、なぜ最後の人間になるのかは、ネタバレしてしまうので書かない)。つまり、ある設定を実現するために、半ば無理矢理作り上げられた人物たちばかりなので、昔の文芸評論家なら手垢にまみれたこんな言葉をはくと思われる。
「人物が全く生きていない」
テーマ、設定ともに抜群におもしろいのに、この部分に関してだけは本当なので困ってしまう。あの「2001年宇宙の旅」にしても、原作、映画ともに人物の印象はほとんど記憶に残らないほど希薄である。考えてみれば実質的な処女作である「太陽系最後の日」も波乱含みの始まりで期待がふくらむものの、途中、地底電車に閉じ込められてもたもたしてとてもうまくまとまっているとは言いがたい。当初から「つなぎ場面」の処理は下手だったわけだ。それでもこの作品が読み継がれているのは、読者が人類の一員であることで素晴らしく溜飲が下がるラストがそれまでの欠点をすべて覆い隠してしまうからだ。
要するにクラークの作品は処女作から最高傑作と言われる「幼年期の終り」、話題になった「2001年宇宙の旅」、晩年の「宇宙のランデブー」に至るまでテーマ、書き方とも(いい意味でも悪い意味でも)終始一貫しているのだ。そんなことから、(めぼしいものはほとんど読んでしまっている今となっては遅いのだが)私はクラーク作品の出来不出来を見分ける重要なキーワードを導き出すことができた。
「会話の少ない小説を読め」
素晴らしく息をのむような状況描写と個性のない人間たちの織りなすドラマなのだから、こういう結論になる。クラークを弁護すれば、世間一般の人間関係などこかへ吹き飛ばしてしまうほど描かれる状況が魅力的かつ鮮烈なのだ。クラークには、人類を継ぐものは人類ではない、それは「2001年」のような機械(コンピュータ)かもしれないし、「幼年期」のような超人類かもしれないという、確固たる信念がある。そうした状況の中では、「人物が生きていない」のではなく「人物が霞んでしまう」のだ。状況描写に場面と比べて人間関係の場面が希薄かつ退屈なのはそのせいなのではないかと思う。だから、クラークの小説は、会話部分が少なければ少ないほどいい。もしも、会話が全然ないクラークの作品があったとしたら、それは間違いなく傑作だと断言してもよい。絶対に読むべし。
※おまけ A.C.クラークの「2001年宇宙の旅」に始まる「オデッセイ・シリーズ」についてはこんな雑文を書いたことがある。関心のある人は、暇潰しにどうぞ。
https://meisoud.blog.ss-blog.jp/2013-05-23




